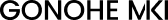オンラインサロン リニューアルのお知らせ
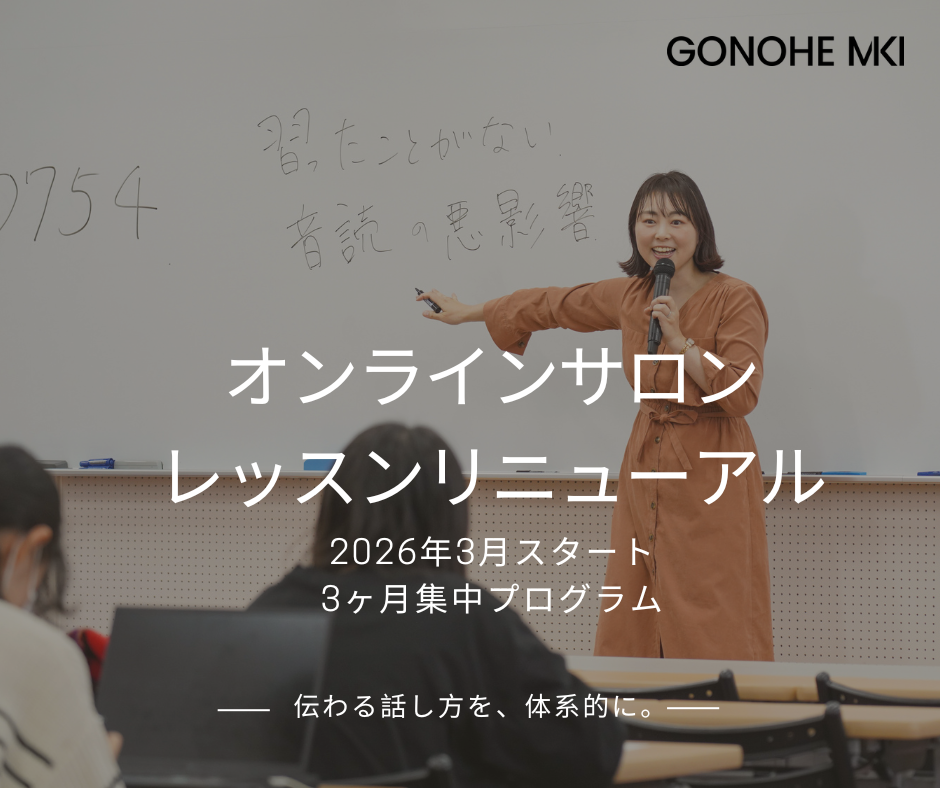
このたび、2026年3月より、
オンラインサロン「五戸美樹のスピーチトレーニングサロン」を
リニューアルいたします!
これまでの受講者の皆さまからの声をもとに、
「より実践に入りやすいレッスン」
「よりスキルが身につく構成」へと
再設計しました。
なぜリニューアル?
これまで、メンバーさんを含め、
たくさんの方の話し方・プレゼン指導に携わってきましたが、
それぞれのお悩みから、
“日本語話者”共通の課題を感じています。
それがこちら
・人前での話し方を習ったことがない
・人前で話す=原稿の朗読 になっている
・自己流でやってきた結果、癖がついてしまっている
スキルアップのためには、
正しい知識を得た上で、
実践トレーニングする場が必要だと
ますます感じるようになりました。
そこで!
今回、サロンのレッスンをリニューアルすることで、
より実践に入りやすく、
より再現性のあるスキル
(毎回同じように成果を出せる)が
身につく構成になるよう
【3ヶ月単位】で
体系的に学べるプログラムへと刷新しました。
何がどう変わった?
サロンのメインコンテンツであるグループレッスンを
【月2回 × 3ヶ月(全6回)】の
集中プログラム形式にいたします。
ポイントはこちら!
・プレゼン構成を、感覚ではなく論理的に組み立てられるよう設計
・原稿を一言一句作らず、自分の言葉で伝える練習プロセス
・緊張時でも安定した声・話し方をコントロール
・フィードバックをもとに、改善を再現できる仕組み
これまで通り、たくさんの人の前であっても
「別人を演じる」ことを目指すのではなく、
自分の良さを生かして、
伝わる話し方へアップデートしていく、
そのためのレッスン形式のリニューアルです。
こんな方におすすめ!
・仕事でプレゼン・説明・発表の機会がある方
・準備しているのに、伝わっている実感が持てない方
・話し方を自己流から脱し、再現性のあるスキルにしたい方
・緊張しやすいが、安定して話せる力を身につけたい方
初心者の方はもちろん、
これまで学習経験のある方の再構築にもおすすめです。
今後のサポート体制・学びの特徴
・Zoomによるオンライン開催(途中参加・途中退出可)
・発言が不安な方は、聞くだけ参加も可能
・サロン内で質問・課題提出・フィードバック対応
・過去アーカイブもすべて閲覧可能
・平日レッスンでは、より専門的・応用的なテーマも継続実施
また、3ヶ月プログラム終了後は、
次のテーマ(朝礼など)へと段階的に学びを深めていく予定です。
継続的にスキルを積み上げたい方にも、
安心してご参加いただけます。
詳細・お申込みについて
プログラム内容やスケジュール、
参加方法など詳しくは、
下記ページをご覧ください。
▶オンラインサロン詳細・お申込みページ
(レッスン内容・日程・参加方法をご確認いただけます)
「活動報告」が「お知らせ」になります

サイトの運用を見直し、
情報をわかりやすく整理することにしました。
今後、活動報告はInstagramにまとめて発信し、
こちらのページでは講座・募集など
重要なお知らせを掲載していきます。
日々の活動の様子は、ぜひInstagramでご覧ください。
Instagramはこちら
InstagramでYouTubeの投稿告知もしています。
YouTube更新!原稿なしプレゼン講座

🎤 プレゼン”原稿なし”で脱線しない話し方3選
「スライドの文字を読まずに話すほうが上手」
だと思っていませんか!?
実はそれ、聞き手に負担をかけ、
伝わりにくくなることも。
原稿なし・スライドだけで成功するプレゼンの基本は
「結論ファースト」の徹底✨
✅ プレゼンの基本の話し方
・スライドの文字は「要約」であり「結論」
・まずはスライドの要約を読み上げる
・その後に説明を足す
✅ スライドだけを見て話す3つのパターン
本番で楽になり、聞き手を飽きさせない話し方!
1, スライドの読み上げ+説明
2, 箇条書きごとに読む+説明
3, 「こちら!」と言ってめくる
(エンタメ性で飽きさせない演出効果)
この3パターンを使いこなせば、
原稿に頼らず、
スライドから脱線することなく、
聞き手に負担をかけないプレゼンが実現します💪
【YouTube】では、さらに詳しくお話しています🎥
【原稿なしプレゼン】スライドだけで話す!結論ファーストで脱線しない3つの型を実演解説 | プレゼン講座②
【ノーカット実演】原稿なしで話す!7分でわかる“結論ファースト”プレゼン
オンラインサロン2025年12月スケジュール

🎤五戸美樹のスピーチトレーニングサロン
2025年12月スケジュール🗓️
・12/5(金)23時59分 11月課題〆切
・12/6(土)10時〜グループレッスン<ボイスサンプル・選択原稿>
・12/11(木)12時〜グループレッスン<ボイスサンプルorフリートーク>
・12/14(日)年末イベント2025<ボイスサンプル収録>
・12/18(木)20時〜もちもちのグループレッスン<フリートーク>
・12/24(水)12時〜グループレッスン<プチ講演・口腔ケア>
・12/29(月)10時〜グループレッスン<絵本読み聞かせ>
■サロン内容✨
・毎週グループレッスン
・毎月課題提出
知識・実践・フィードバックで着実にトークスキルが向上するサロンです🙆♀️
■今後のイベント✨
・12/14(日)ボイスサンプルを収録するイベントを開催🎤
同日夜は忘年会😆🍺
■11月の活動報告✨
・ボイスサンプル収録に向け、
グループレッスンは原稿読み強化月間📅でした
・メンバーさん主催の練習会が開催されました👏
・サロンスタッフ・しほさんのボイトレ講座も開催🗣️
・メンバーのアグネスさんのラジオに、メンバーのスミノさんがゲスト出演📻🥰
サロン詳細はこちら
https://lounge.dmm.com/detail/2215/
YouTube更新!暗記しないプレゼン講座
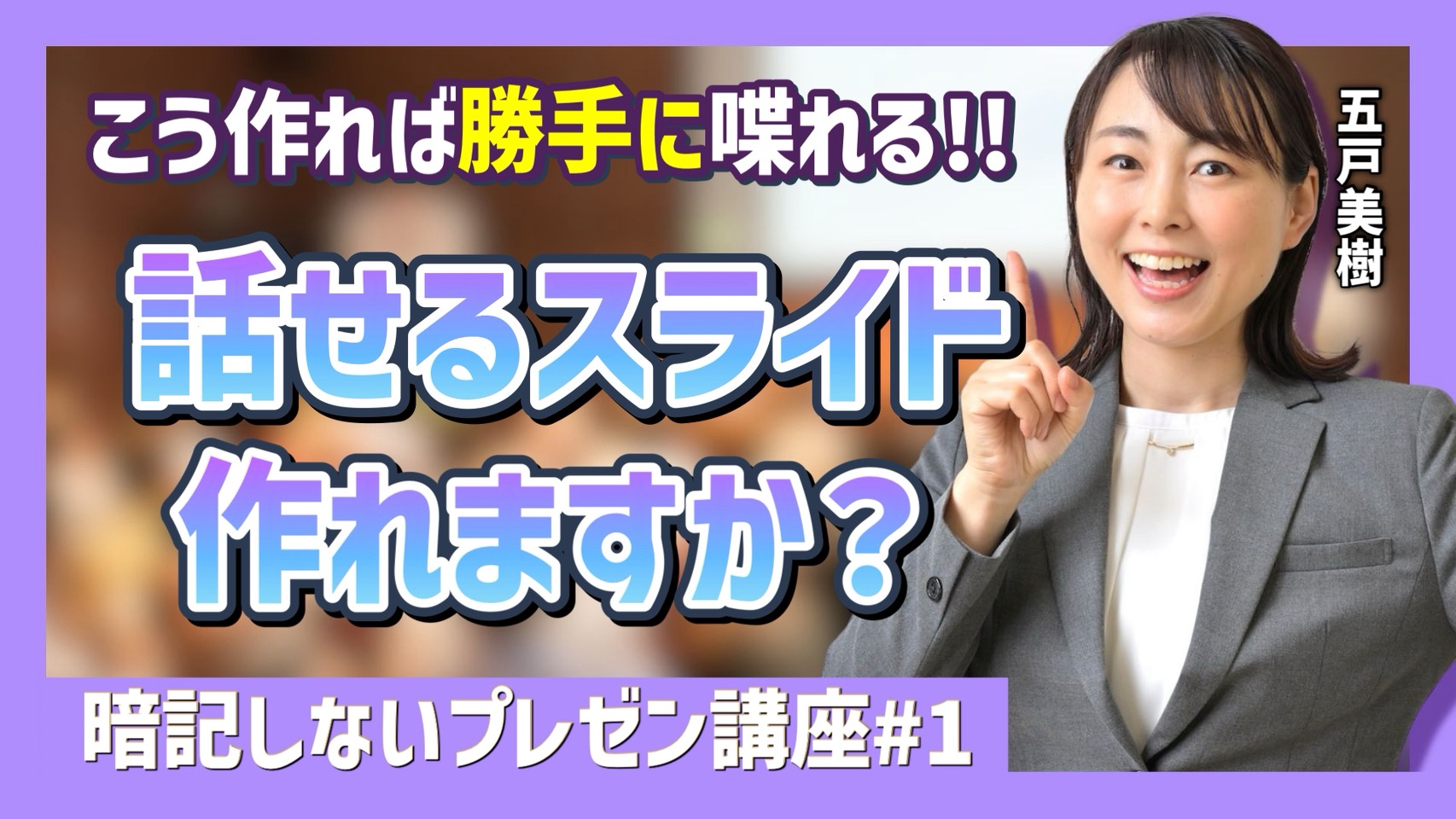
「原稿なしでプレゼンしたいけれど、丸暗記はムリ…」
そんな方におすすめなのが、
“原稿のいらないスライド制作”です✨
ポイントは2つ👇
① 最初に“ざっくり全体像”を作る
いきなりスライドには行かず、
まずは<話したいことを箇条書き>で最後まで。
道路地図をつくるイメージ🗺️
これがあると、話が迷子にならず、原稿も不要に。
② 全体像を「プログラム」に分ける
話の区切りごとに章立てすると…
・自分の進行が把握しやすい📍
・聞き手にも流れが伝わる👂
・タイムキープ(ラップ)が簡単⏱️
③要約をスライドに
①②を整えてから
要約をスライド化すると、
スライドと別に原稿を作らなくても
“伝わるプレゼン”が実現🎤
練習時間が取れないビジネスパーソンにもおすすめです!
【YouTube】では、さらに詳しくお話しています🎥
原稿なしで話せるスライドの作り方|説明がうまくいかない原因と改善ステップ【プレゼン講座①】
YouTube更新!就活面接・丸暗記に頼らず答える方法
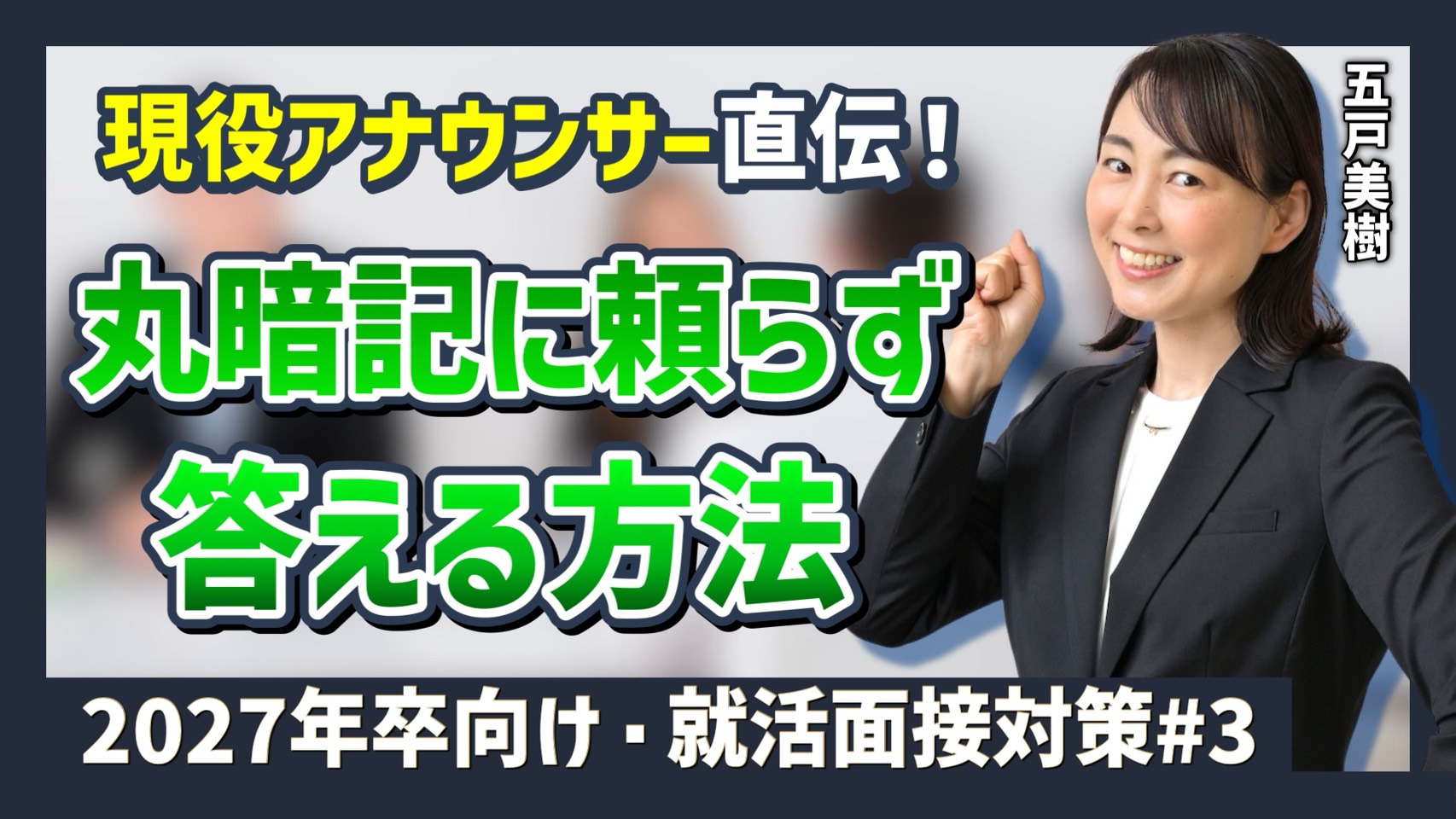
\ 就活面接で“話せない”原因はコレ! /
今回は「暗記が逆効果な理由」と
「自然に話せる回答づくり」をまとめます🫡
【❌丸暗記がダメな理由】
・朗読ではコミュニケーションにならない…
・想定外の質問に弱い…
【⭕自然に話す3ステップ】
1️⃣ エピソードを決める(1つでOK)
例:ダンスサークル、アルバイト、ゼミ etc.
2️⃣ 原稿を一言一句つくらない
→ 箇条書きで整理するのが最強!
※足りなければ後から足すだけでOK!
3️⃣ “話しかける相手”を決めて練習
✔ 敬語で話す相手(先輩・先生など)
✔ 写真をパソコンに貼る
✔ Zoomを立ち上げ「その人に向けて」話すつもりで練習
👉 話しかける意識があると、自然な語り方に変わる!
【🔍どうして大事なの?】
面接官は「正しい言葉遣い」より、
“会話になるか” “人間性はどうか” を見ています。
話しかける練習をすることで、
暗記の朗読ではなく “対話” に!
深掘り質問がもらえるようになります。
【YouTube】では、さらに詳しくお話しています🫡
就活面接|暗記は逆効果!自然に話せる“回答の作り方”【27卒・第3回】
今後の対面グループレッスンのお知らせ

先日、土日開催の対面グループ・コース講座が最終回を迎えました🌿
ご参加くださった皆さま、ありがとうございました✨
初日と最終日にそれぞれ動画撮影を行ったのですが、
皆さん、内容も話し方も声も本当にスキルアップされていて、
とても嬉しく、講師としてやりがいを感じました☺️
さて!
今後のグループレッスンのお知らせです📢
🌸月一回・平日お昼に開催!
1回完結の対面グループレッスンとして続けていきます🎤
次回の対面グループレッスンは、
📅 12月5日(金)12:00〜
💡 ストアカにて受付スタート!
スピーチトレーニング・対面グループレッスン(ストアカ)
少人数制で、講義も実践もできる講座です✨
人前トークの不安は知識と実践で解決できる!と思っています💪
初めてのスピーチトレーニングにおすすめです😊
P.S.
コース講座の次回リクエストもいただくのですが、子どもがまだ幼いので、土日に家を空けるのが難しいこともあり、コース講座の形は一区切りとさせていただきました🙇♀️
個別レッスンも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください🙏✨
YouTube更新!就活・強みと志望動機の答え方
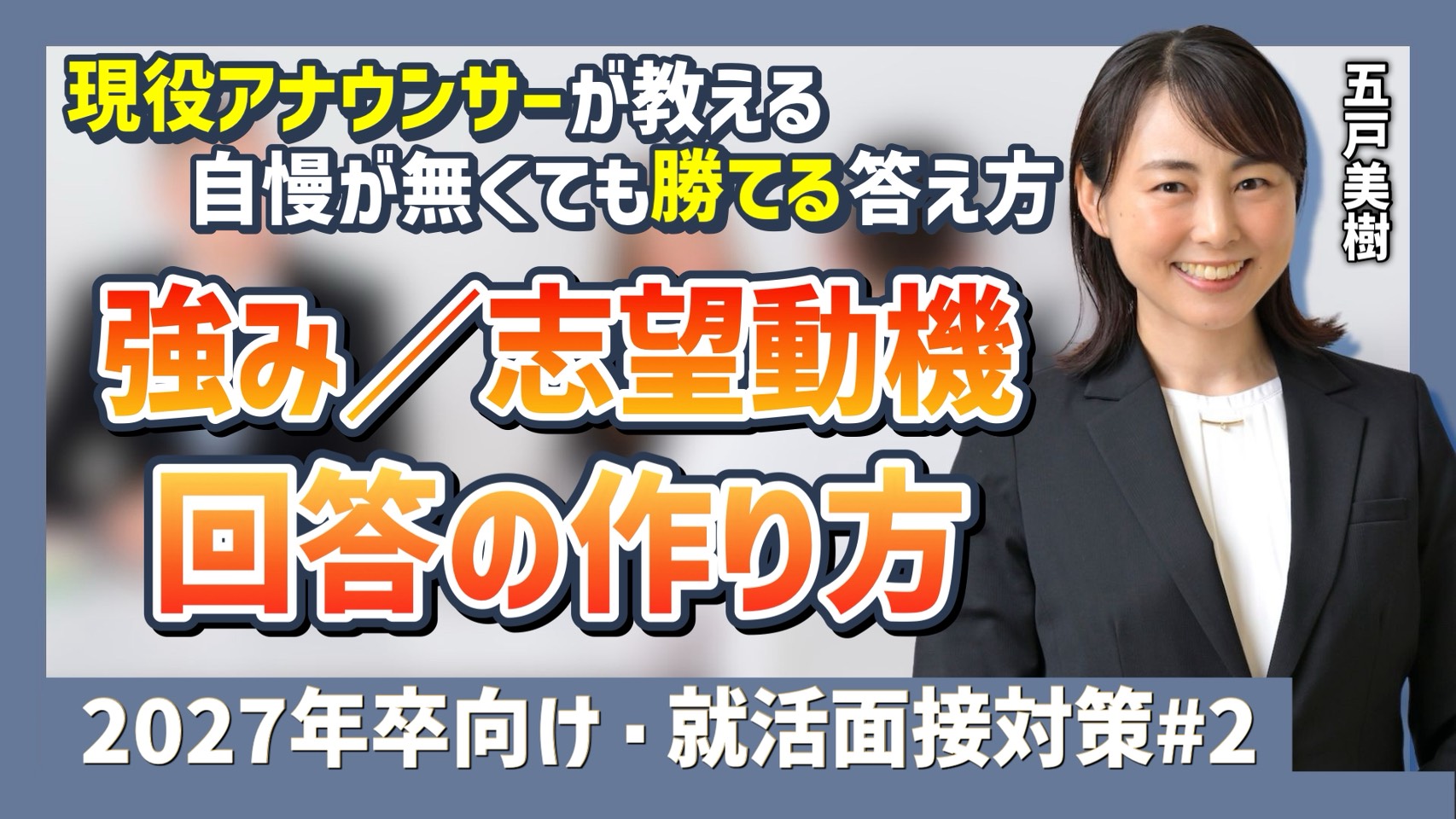
🎯 就活面接の定番質問3つを攻略!
「強み」「志望動機」「会社に入ってやりたいこと」
面接で何を話せばいいか迷っている’27卒の学生さん院生さんへ!
実践できるポイントをまとめました👇
1️⃣ 強み
💡「協調性です」はおすすめしておりません🥲
まずはエピソードを思い出して
そこから自分の強みを導き出してください💪
例:
🎸軽音楽サークルでスタジオ予約を調整
→ 強みは「交渉力」や「調整力」
2️⃣ 志望動機
💡 企業理念の丸暗記は不要です🙅♀️
説明会やOB訪問で感じた
具体的な魅力を話してください🙆♀️
3️⃣ 会社に入ってやりたいこと
💡実現性よりも「具体性」を意識するのがおすすめ👍
自分の経験や興味と関連づけると説得力UPです!
💬 面接は「自分という新商品をプレゼンする場所」
自分の経験を整理して、自分らしい回答を考えてくださいね✨
【YouTube】では、さらに詳しくお話しています。
就活面接の定番質問3つを攻略!「強み・志望動機・やりたいこと」の答え方【27卒・第2回】
YouTube更新!就活・面接の準備方法
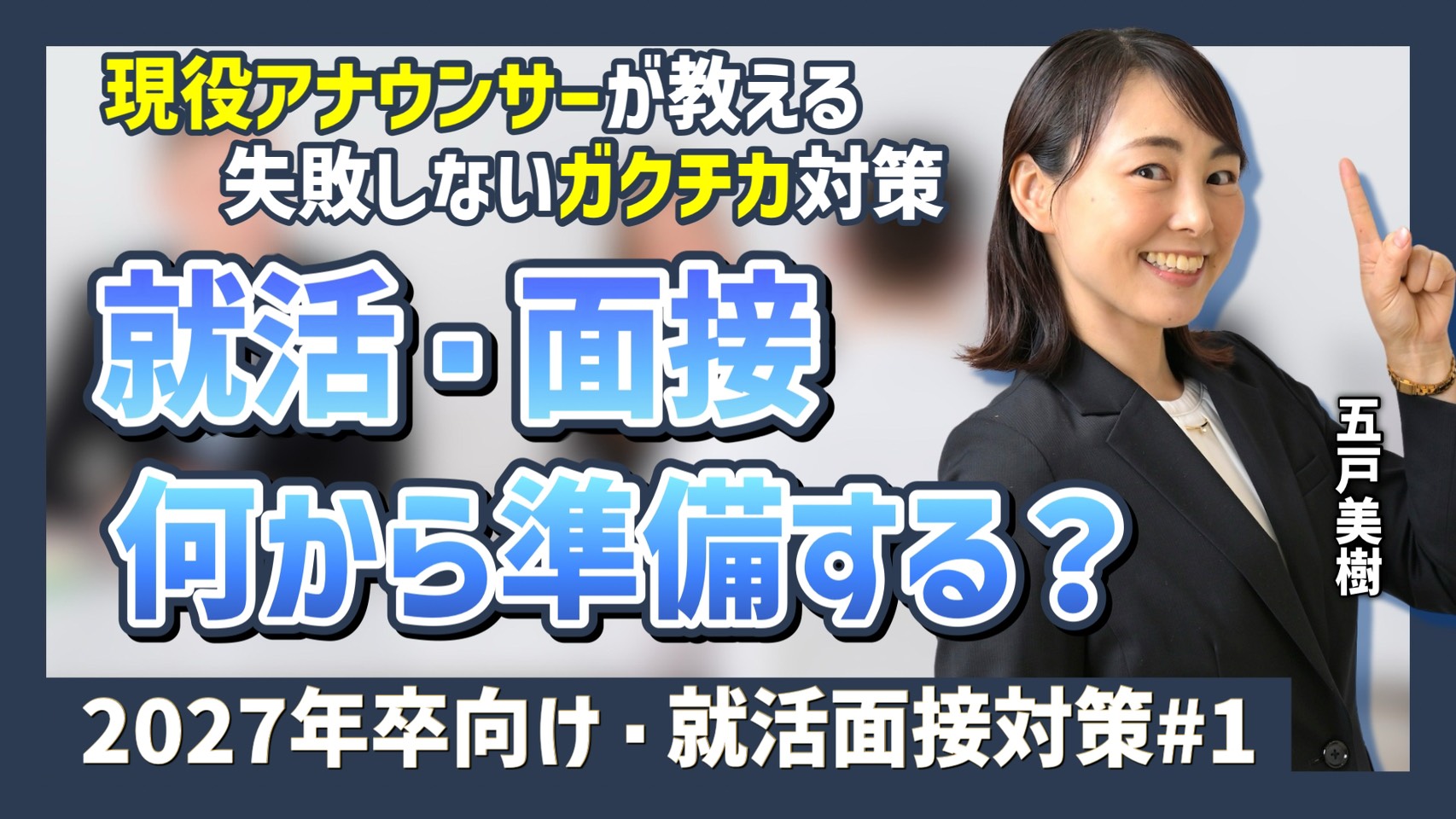
「そろそろ就活、と思ってはいるけれど
何から始めたらいいかわからない…🥲」
そんな学生・院生の皆さんへ!
就活の面接準備、まずはこちら💁♀️
🎯「ガクチカ」を完成させる!
よくあるのが…
「授業もサークルもバイトも!」と詰め込むこと。
でも面接は、一方的に話す場所ではなく
“対話”で人柄を見てもらう時間です。
だからこそ、
✅力を入れたことは1つに絞る
✅エピソードで具体的に語る
この2つがとても大事🙆♀️
「たいしたことしてない…」と思う方は、
生成AIにインタビューしてもらって
エピソードの棚卸しをしてみてください✨
応援しています🔥
【YouTube】では、さらに詳しくお話しています。
就活面接の準備はこれでOK!まず何をやる?’27卒向け完全ガイド|シリーズ第1回
オンラインサロン2025年11月スケジュール

🎤五戸美樹のスピーチトレーニングサロン
2025年11月スケジュール🗓️
・11/5(水)23時59分 10月課題提出締め切り
・11/8(土)10時〜11時 グループレッスン<司会・エンタメ系>
・11/8(土)20時〜21時 しほのグループレッスン<ボイトレ&エピソードトーク>
・11/13(木)12時〜13時 グループレッスン<ボイスサンプル・選択原稿>
・11/18(火)12時〜13時 グループレッスン<プチ講演・口腔ケア>
・11/29(土)12時〜13時 グループレッスン<ボイスサンプル・選択原稿>
・11/30(日)23時59分 年末イベントお申込締切
■サロン内容✨
・毎週グループレッスン
・毎月課題提出
知識・実践・フィードバックで着実にトークスキルが向上するサロンです🙆♀️
■今後のイベント✨
・12/14(日)ボイスサンプルを収録するイベントを開催🎤
同日夜は忘年会😆🍺
■10月の活動報告✨
・明日から「司会できます」と言えるような準備方法やヘアメイクをレクチャー
・サロンスタッフ・もちもちさんのレッスンで映像ナレーションにチャレンジ
・メンバーさんが動画やアクセントをシェアしてくれました☺️
・メンバー・アグネスさんのラジオが半年継続&メンバーさんが番組見学で盛り上がりました📻✨
五戸美樹のスピーチトレーニングサロン
https://lounge.dmm.com/detail/2215/